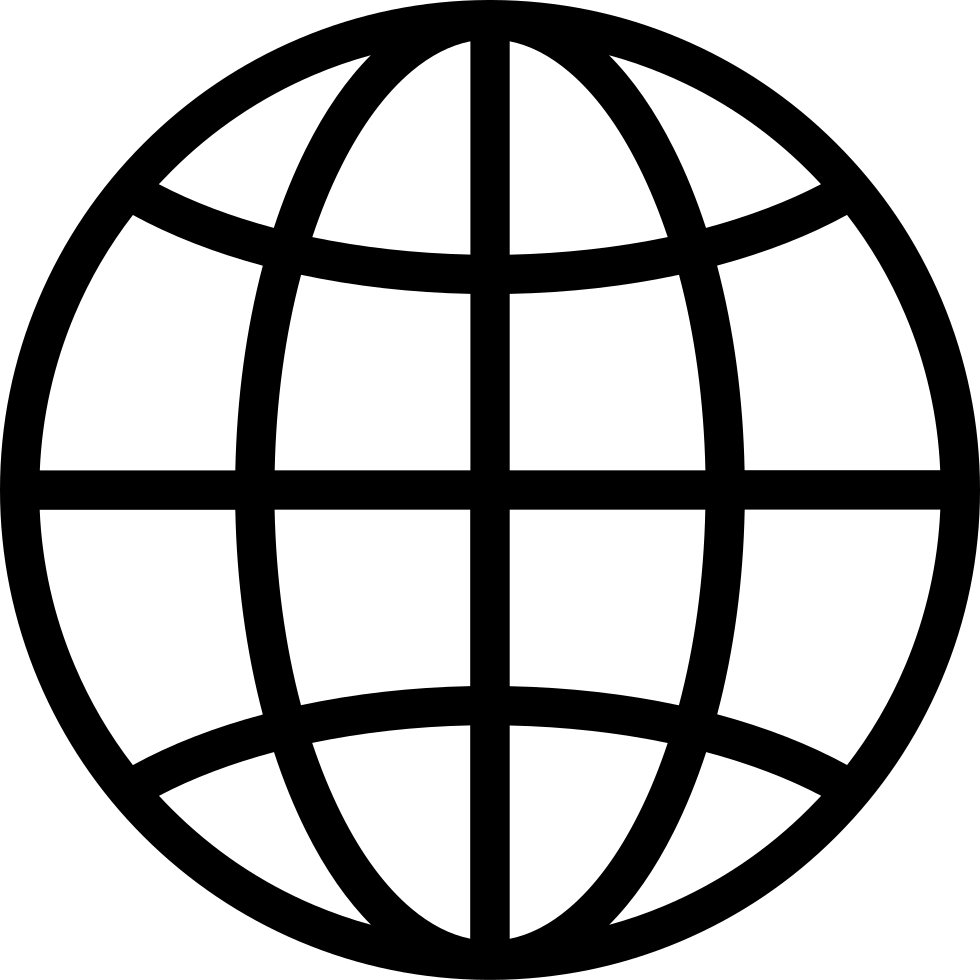#36 屋敷神④ なぜイナリとウジガミという違いが生じた?
Manage episode 383470897 series 3528353
屋敷神の第4回です!
今回でこのテーマは終了です★
関東地方の4カ所
・埼玉県東松山市
・東京都東久留米市
・埼玉県和光市
・栃木県真岡市
を調査したところ、ウジガミ系とイナリ系に大きく分けることができました。
そこで、江戸時代の町方での稲荷信仰の様子を文献から確認して、関東地方での屋敷神の変遷について論じます。
音声の音声の説明だけだとわかりにくいかもしれないので、こちらより文章もご確認下さい。
そして今回、ちょっと聞き取りにくい部分があるので、補足します。
14:45の部分は「北条氏の旧領に国替え」
16:50の部分は「『江戸朱引図』というものを示します」
と言っています(汗)
そしてぜひ、皆さんの知っている屋敷神の情報も教えてください。
こちらのフォームから募集します。
また、6月のトーク会「やさしい民俗学 − 暮らしをひもとく二人話 − 」のテーマは「七夕(たなばた)」です。
ご興味のある方は、こちらのページでご確認&お申し込みをお願いします♪
【今回のポイント】
岡山県真庭市のこと/柳田と折口の話が多いことについて/民俗学の反省とこれから/関東地方の4箇所での調査結果からウジガミ系とイナリ系に分類/この違いはなぜ?/江戸期の文献を確認/斎藤月岑『武江年表』/江戸の街でイナリが流行/江戸近郊の農村にも影響があったか/ウジガミからイナリへと上書き/都市からの文化の伝播の様子が伺えた 【参考文献】
岸澤美希 2018年「関東地方の屋敷神 −ウジガミとイナリ−」(新谷尚紀編『民俗伝承学の視点と方法 −新しい歴史学への招待−』吉川弘文館)
1968年『増訂 武江年表1・2』平凡社
79 つのエピソード