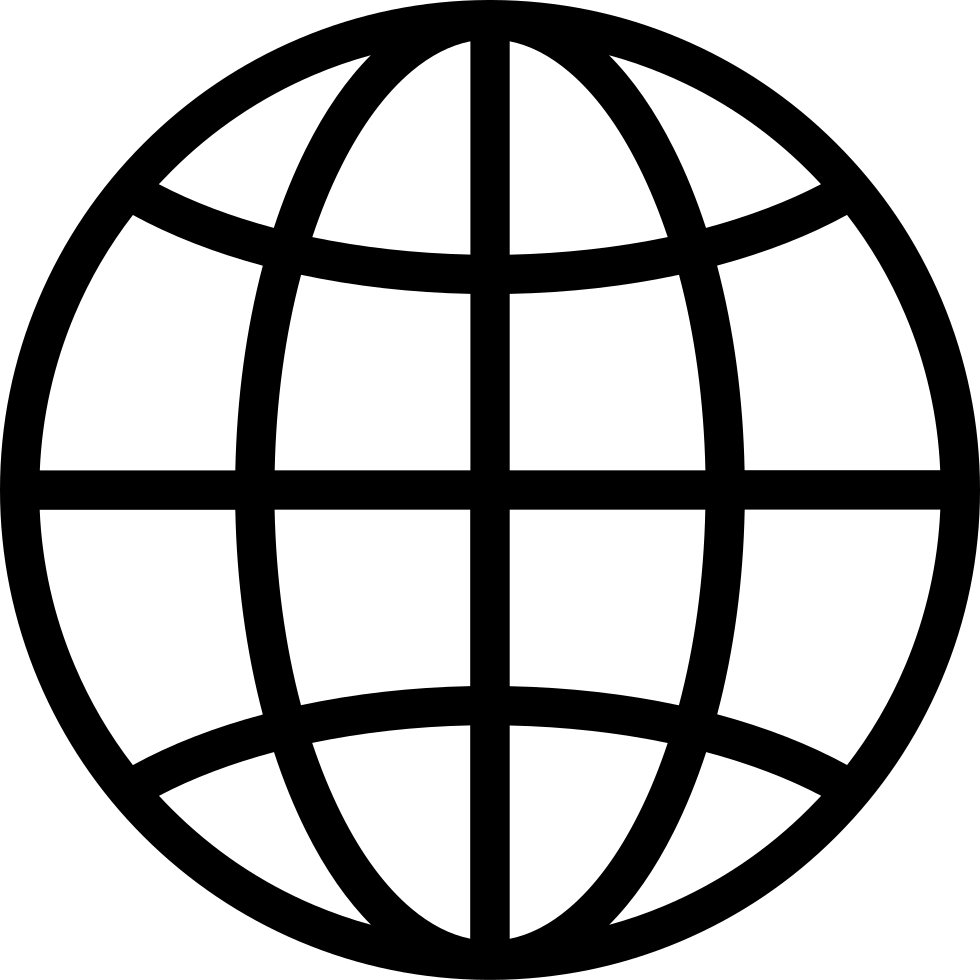#55 お雑煮③ その味付けは静かに変わっている?
Manage episode 394068371 series 3528353
お雑煮の3回目です。
前回、全国のお雑煮の分布と、味噌と醤油の来歴について確認してみましたが、今回はお雑煮の味付けの変遷について文献と民俗事例を見て考えてみました。
◆◆◆◆◆
皆さんのお雑煮の情報はコチラから聞かせてください
https://forms.gle/Gi83EUrVZFXPW2FV9
◆◆◆◆◆
【今回のポイント】
垂れ味噌とは?/味噌を溶いて漉した液体調味料があった/味噌のすまし汁は醤油よりも早い/徳川家が醤油のすまし汁のお雑煮になったのは18世紀中期頃か?/江戸後期には江戸の町方ではみんながお雑煮を食べた/醤油のすまし汁のお雑煮を普及させたのは参勤交代?/幕府直轄領の京都・大阪には影響が少なかった?/味噌から醤油のすまし汁の変遷は昔の話ではない/
民俗資料からわかるその変遷/「正月料理だけは醤油を使う」/「人の意思の加わり得る限りは外部からの浸潤が力を発揮する/毎年のお雑煮だって少しずつ変わっているかも!
【参考文献】
瀬川清子 1956年『食生活の歴史』花島書店
斎藤月岑著・朝倉治彦編 1970年『東都歳時記』 東洋文庫
辻善之助 編 1991年『鹿苑日録』続群書類従完成会
柳田國男 1964年「郷土誌論」(『定本柳田國男集』25巻)筑摩書房
喜田川守貞 1996年『守貞漫稿』岩波文庫
奥村彪生 2016年『日本料理とは何か―和食文化の源流と展開―』農山漁村文化協会
白石知子 2018年「伝統的食文化の継承とその環境(その3)」(宮崎学園短期大学紀要 10号)
79 つのエピソード