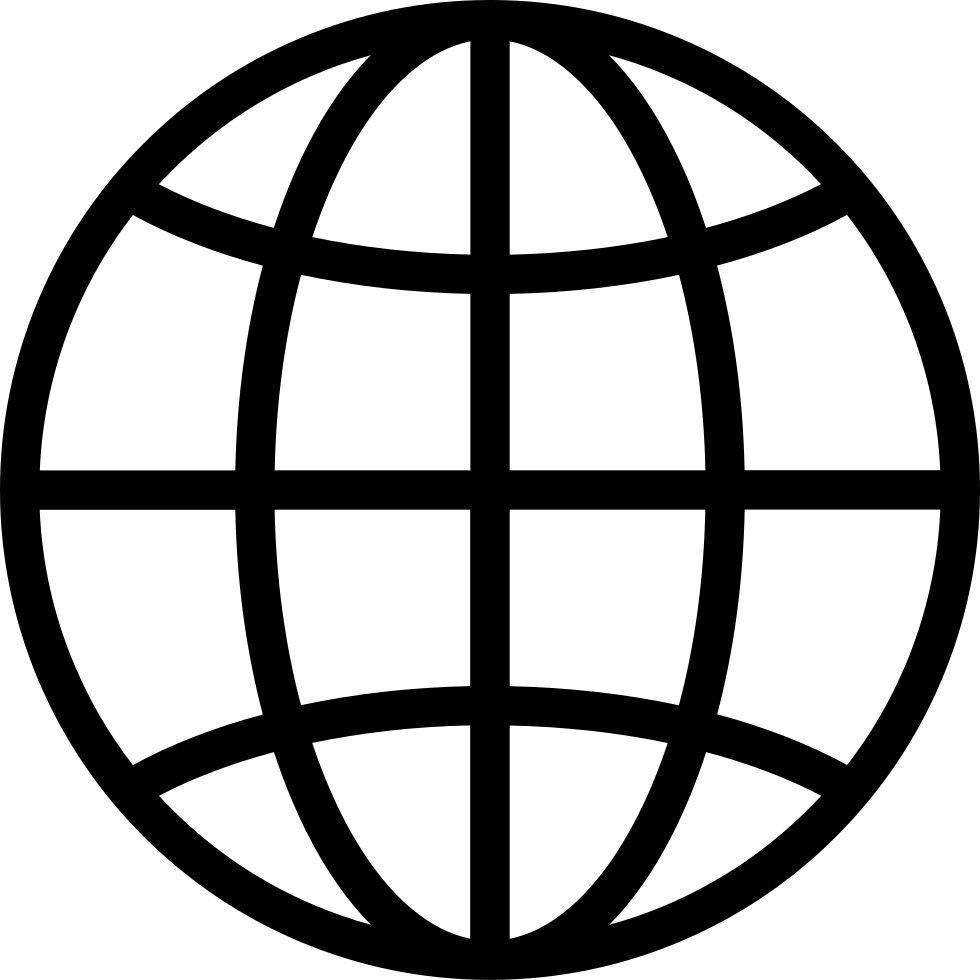面白かった本について語るポッドキャスト&ニュースレターです。1冊の本が触媒となって、そこからどんどん「面白い本」が増えていく。そんな本の楽しみ方を考えていきます。 bookcatalyst.substack.com
…
continue reading
テクノロジーを駆使して、仕事や生活がちょっと便利に、楽しくなるテクニックをお届けする番組です。平日お昼に毎週更新。1話1テーマ。 Obsidianやそれに関連する話、自作キーボードと日本語入力なんかの話が最近は多いです。
…
continue reading
今回はデイモン・セントラの『CHANGE 変化を起こす7つの戦略: 新しいアイデアやイノベーションはこうして広まる』を取り上げました。 書誌情報 * 原題 * 『CHANGE:How to Make Big Things Happen』 * 出版日 * 2024/1/25 (原著:2021) * 出版社: * インターシフト * 著 * デイモン・セントラ * ペンシルヴェニア大学のコミュニケーション学、社会学、工学の教授。 * 翻訳 * 加藤万里子 * 『アナログの逆襲』など 目次や今回の内容に関係する倉下の読書メモは以下のページにまとめてあります。 ◇ブックカタリストBC088用メモ - 倉下忠憲の発想工房 「弱い絆」を再考する 昨今のビジネス書などでは、「弱い絆」が重要だとよく言われま…
…
continue reading
面白かった本について語るPoadcast、ブックカタリスト。 今回は(最初はシンセサイザーの話をしようと思ってたのにいつのまにかその導入部分が広がって)『音楽の人類史:発展と伝播の8億年の物語』のごく一部の部分だけを紹介しました。 ごりゅごの今年のブックカタリストのテーマは「つなげる」だって言っといて、今度は逆に「一回で一冊分を取り上げていない」というこの感じ。 これは、次回と「つなげる」ことを目指しているが故に起こった現象です。 こういう屁理屈が得意になったのも、ブックカタリストを長年続けてできるようになったことです。 次回の予定は(ごりゅご回は約一ヶ月後の公開ですが)「シンセサイザー」なんかの話の予定です。それはおそらく「物理と音楽」をつなげる話。今回は「歴史と音楽」をつなげる話。 今年…
…
continue reading
今回は二人が読んだ『体育館の殺人』というミステリー小説から「本の読み方」について考えます。 「読者への挑戦状」への挑戦 発端は、倉下が『体育館の殺人』を読んで「読者への挑戦状」にきちんと挑戦しよう、という試みです。そこにいたる流れは二つありました。 まず一つは、アニメ『アンデッドガール・マーダーファルス』で青崎有吾さんに興味を持ち、以前から面白い作品を書く人だと聞き及んでいたので、じゃあ一作目の『体育館の殺人』を読んでみようという流れ。 もう一つは、一冊の本を一年かけて複数人で読んでいこうという環読プロジェクトや、毎日少しずつ本を読みその読書日記を書くという「ゆっくり本を読む」という自分の中でのマイテーマな流れ。 その二つが合流することで、ミステリー小説の「読者への挑戦状」にガチンコで挑戦し…
…
continue reading
今回取り上げるのは、山本貴光さんの『文学のエコロジー』です。 本書を通して、「文学を読むときに何が起きているのか?」を考えてみます。 書誌情報 * 著者:山本貴光 * 哲学の劇場でもおなじみ * 『記憶のデザイン』『文学問題F+f』などがある * 出版社:講談社 * 出版日:2023/11/23 * 目次: * プロローグ * 第I部 方法——文学をエコロジーとして読む 19 * 第1章 文芸作品をプログラマーのように読む 20 * 第II部 空間 49 * 第2章 言葉は虚実を重ね合わせる 50 * 第3章 潜在性をデザインする 74 * 第4章 社会全体に網を掛ける方法 97 * 第III部 時間 117 * 第5章 文芸と意識に流れる時間 118 * 第6章 二時間を八分で読むとき、…
…
continue reading
今回は、jMatsuzaki さんをゲストにお迎えして、新刊『先送り0(ゼロ)―「今日もできなかった」から抜け出す[1日3分!]最強時間術』についてお話をうかがいました。 書誌情報 * 出版社 * 技術評論社 * 出版日 * 2024/2/24 * 著者 * jMatsuzaki * 1986年生まれ。クラウドサービス「TaskChute Cloud」開発者。jMatsuzaki株式会社 /jMatsuzaki Deutschland UG代表取締役。一般社団法人タスクシュート協会 理事。 * システム系の専門学校を卒業後、システムエンジニアとして6年半の会社員生活を経て独立。会社員時代にjMatsuzakiの名で始めたブログが「熱くて有益」と人気を博し、最高で月間80万PVに達する。現在は…
…
continue reading
1
BC083 『ザ・フォーミュラ 科学が解き明かした「成功の普遍的法則」』と『残酷すぎる人間法則』の2冊から考える人間関係
1:07:07
1:07:07
「あとで再生する」
「あとで再生する」
リスト
気に入り
気に入った
1:07:07
面白かった本について語るPoadcast、ブックカタリスト。今回は『ザ・フォーミュラ 科学が解き明かした「成功の普遍的法則」』と『残酷すぎる人間法則』の2冊から考える人間関係をテーマに語りました。 ごりゅごの今年のブックカタリストのテーマは「つなげる」です。 ブックカタリスト本編の中で、2冊の本をつなげて語りつつ、その内容は前回ともつながることを意識しています。 3年くらいブックカタリストを続けて、ようやくこういう切り口で本を紹介できるようになったぞ、という感じがしています。 これ、3年前に同じことをやったとしても、もっと「無理やり」な感じになったような気がします。 今年公開した2回は、よい意味で「無理してつながりを見つけようとして読んでいない」本で、3年分の読書メモの蓄積があって、そこから…
…
continue reading
今回は、2023年11月に発売となった『思考を耕すノートのつくり方』を著者自身が紹介します。 書誌情報 * 著者 * 倉下忠憲 * 出版社 * イースト・プレス * 出版日 * 2023/11/17 * 目次 * はじめに * Chapter 1 知的道具としてのノート * 「頭の中だけ」は限界がある/頭の使い方のサポート/気軽に、自由に使う * Chapter 2 使い方のスタイル * ノートの種類/罫線の意味/サイズ/紙質と使い心地/ページ/タイムスタンプの重要性/ナンバリングの利便性/貼りつける etc. * Chapter 3 書き方のスタイル * 日記/作業記録/メモ(アイデアメモ)/講義ノート/タスクリスト/ * 会議・打ち合わせノート/着想ノート/思考の整理/研究ノート/読書記…
…
continue reading
Amazon.co.jp: 「公式」Creality Ender 3 S1 3Dプリンター 迅速な組立 自動水平調整 96%組立 デュアルZ軸スクリュー PCシート FDM 3Dプリンター 停電復帰 鋼製プリントベッド 造形サイズ220x220x270mm 日本語の操作とマニュアル : 産業・研究開発用品 ご意見、ご感想はTwitterのハッシュタグ#ごりゅごcastかお便りフォームにお送りください。
…
continue reading
面白かった本について語るPoadcast、ブックカタリスト。今回は『ピダハン』と『ムラブリ』という2つの民族から考える新しい価値観について語りました。 ムラブリは読んでから半年以上、ピダハンは1年以上経過している本ですが、どちらも今でも強く印象に残っていて、読書メモもそれなりにきちんと残っています。 そのおかげで、メモを見ながらであれば、だいたいのことを思いだすことができて、だいたいのことは「語る」ことができるようになったな、と実感した回でした。 ブックカタリストを始めて、現在で大雑把に3年くらいが経過。やはり、そのくらいの期間続けていると、いろいろなことが「スキル」として身に付いてきたな、と感じられています。 今回は(たぶんごりゅごとしては珍しく)テーマを設けて、そのテーマに従って本の紹介…
…
continue reading
2024年一発目の配信です(収録は去年行われました)。 今回は倉下が『ゲンロン0 観光客の哲学』と『哲学の門前』の二冊を取り上げ、それぞれのエッセンスを通して「本を読むこと」について考えるという構成になっております。 最初に結論を述べておくと、専門家ではない僕たちは自らの興味に沿って、なかば偶発的に本を読んでいけばいいんじゃね、という話です。 配信に使用したメモは以下のページからご覧いただけます。 ◇ブックカタリストBC080用メモ - 倉下忠憲の発想工房 観光客の哲学 観光客とは何か、あるいは観光客の哲学とは何か、というのは本編で扱っているのでそちらをお聞き頂くとして、やはり重要なのは人間は「動物的」なものと「人間的」なものの二層でできているという視点でしょう。そうした二層構造は、去年の『…
…
continue reading
前回に引き続いて、今年一年の配信の振り返りです。 ◇2023年ブックカタリスト配信リスト - BCBookReadingCircle 上記ページの「----half---」より下の回を振り返ります。 当記事では、倉下視点でのトータルの振り返りを。 リアルなものの復興・二重構造 まず『言語はこうして生まれる』および『会話の科学』で、私たちのリアルで日常的な会話の重要性が回復されました。理論的に整ったものが「本質」ではなく、雑多で即興的なやりとりこそが言語の中心的な意義であると確認されたわけです。 その上で、『ふつうの相談』の構図が立ち上がります。論理的に整ったものや体系的なものは、ある特殊な状態を先鋭化させたものであり、そうした研究にはたしかに意義がある。しかし、私たちのリアルはもっと柔軟で雑…
…
continue reading
1年の振り返りにどんなツールを使っているのか これを踏まえて、次回は1年を振り返りをしてみようと思ってます。 ご意見、ご感想はTwitterのハッシュタグ#ごりゅごcastかお便りフォームにお送りください。
…
continue reading
毎年恒例になりつつある、今年の配信の振り返りです。 配信のリストは以下にまとめてありますので、ご覧ください。今回はこの上半分を振り返りました。 ◇2023年ブックカタリスト配信リスト - BCBookReadingCircle とりあえず、今年一年も大きなトラブルなく続けることができました。おそらく一番の成果がそれでしょう。これもひとえにいつもご視聴くださっている皆様、そしてご支援下さっているサポーターの皆様のおかげです。ありがとうございます。 振り返りの意義 倉下は記録魔ではありますが、振り返り魔ではありません。どちらかと言えば、振り返っている暇があるなら、少しでも何かを前に進めたいという前進主義者と言えるでしょう。そんな私であっても、こうして折りに触れて振り返ることの意義を感じています。…
…
continue reading
キャンピングカーレンタル・カーシェア予約はCarstay | バンライフ・ペット旅・ワーケーションを誰でもかんたんに ご意見、ご感想はTwitterのハッシュタグ#ごりゅごcastかお便りフォームにお送りください。
…
continue reading
前回に続いて今回も二人共が読了した本です。 『言語はこうして生まれる』 紹介しようしようと思いながら、なかなか全体がまとめきれないので時間がかかってしまいました。非常にエキサイティングで、抜群に知的好奇心が刺激される一冊です。 書誌情報 * 原題 * 『THE LANGUAGE GAME:How Improvisation Created Language and Changed the World』 * 著者 * モーテン・H・クリスチャンセン * デンマークの認知科学者 * 米コーネル大学のウィリアム・R・ケナンJr.心理学教授 * オーフス大学言語認知科学の教授 * ニック・チェイター * イギリスの認知科学者・行動科学者 * 『心はこうして創られる 「即興する脳」の心理学 …
…
continue reading
1
BC076 『音律と音階の科学 新装版 ドレミ…はどのように生まれたか (ブルーバックス)』
1:05:40
1:05:40
「あとで再生する」
「あとで再生する」
リスト
気に入り
気に入った
1:05:40
面白かった本について語るPoadcast、ブックカタリスト。今回は『音律と音階の科学 新装版 ドレミ…はどのように生まれたか (ブルーバックス)』について語りました。 今回は、ごりゅごが5月にギターを始めてから、約半年で学んだ「音楽の面白さ」の集大成みたいな話をしました。 「音楽の上達」を目指してギターを独学する体験を通じて、ブックカタリストのように「本を読んで何かを語る」というものとはまた違う、新しい「学び方」を知ることができています。 一般的に読書という行為には、肉体的な技能の重要性はほとんどありません。 このジャンルの「学び方」は、これまでにけっこういろいろな本を読んで学んできましたが、ギターを弾くみたいな、肉体的な技能を身に付ける方法はきちんと考えたことがありませんでした。 ただ、ギ…
…
continue reading
「ブログ」から「ウェブサイト」になりました 🏠トップページ - ごりゅご.com ご意見、ご感想はTwitterのハッシュタグ#ごりゅごcastかお便りフォームにお送りください。
…
continue reading
今回は、倉下とごりゅごさんが両方とも読んでいる本だったので、二人で語り合う形になりました。とりあげたのは、『悪意の科学』です。 書誌情報 * 著者 * サイモン・マッカーシー=ジョーンズ * ダブリン大学トリニティ・カレッジの臨床心理学と神経心理学の准教授。 * 翻訳 * プレシ南日子 * アレックス・バーザ『狂気の科学者たち』 * サンドラ・アーモット&サム・ワン『最新脳科学で読み解く0歳からの子育て』など * 出版社 * インターシフト * 出版日 * 2023/1/24 * 目次 * はじめに・・人間は4つの顔をもつ * 第1章・・たとえ損しても意地悪をしたくなる * 第2章・・支配に抗する悪意 * 第3章・・他者を支配するための悪意 * 第4章・・悪意と罰が進化したわけ * 第5章・…
…
continue reading
プラスが付く(iCloudにお金を払う)と、iCloudでできることが増えるのです。 iCloud+ - Apple(日本) ご意見、ご感想はTwitterのハッシュタグ#ごりゅごcastかお便りフォームにお送りください。
…
continue reading
ESRのケースとか充電器、見た目残念だと思ってたら、非常に優秀なやつでした 15W 3 in 1 充電器: https://amzn.to/3FbByFT 折り畳み式充電器: https://amzn.to/46BPMvG 車載用: https://amzn.to/3ZN2YLX ご意見、ご感想はTwitterのハッシュタグ#ごりゅごcastかお便りフォームにお送りください。
…
continue reading
今回は、倉下の直近の新著『ロギング仕事術』を著者自身が紹介しました。 本の内容の直接的な紹介というよりは、この本の背後にあった想いを多めに語っております。 本の主題 「記録をしながら、仕事をしよう」という新しいワークスタイルを提案しています。 そのワークスタイルによって、 * 行為実行中の注意の舵が取れるようになる(短期の効能) * 情報が保存され、再利用可能になる(中期の効能) * 「考える」が起こりやすくなる(長期の効能) といった「うれしいこと」が起こりやすくなります。 倉下が考えるに、この「うれしいこと」は現代において切実にその必要性が高まっている要素です。なので、仕事のやり方を変えたい、仕事をもっとうまく進められるようになりたいという方は、ぜひ「記録をしながら、仕事をする」をやって…
…
continue reading
iOS 17 - Apple(日本) ご意見、ご感想はTwitterのハッシュタグ#ごりゅごcastかお便りフォームにお送りください。
…
continue reading
iPhone13 mini → iPhone15 Pro すごく大きくなって重たくなったけど、とにかく信じられないくらい動作は軽快になりました。カメラの起動が速いと、こんなに気分がいいのか、というのが驚きだった。 ご意見、ご感想はTwitterのハッシュタグ#ごりゅごcastかお便りフォームにお送りください。
…
continue reading
1
BC073『会話を哲学する コミュニケーションとマニピュレーション (光文社新書)』
1:04:09
1:04:09
「あとで再生する」
「あとで再生する」
リスト
気に入り
気に入った
1:04:09
面白かった本について語るPoadcast、ブックカタリスト。今回は『会話を哲学する コミュニケーションとマニピュレーション (光文社新書)』について語ります。 今回は、前回の『会話の哲学』つながりというか、科学で考えた「会話」を、哲学の方面でも考えてみよう、みたいなのがメインテーマです。 最近のブックカタリストは、本編での「対話」によって、事前準備とはまったく違う新しい思いつきがたくさん出てくるようになり、これまで以上に収録が非常に面白いものになってきています。 たとえば「規範的である」ことが人間関係に動影響するのか。この辺の話は事前に準備していたものでなく、話してる流れで自然に出てきたものです。「あえて規範的でない行動をすること」ってたしかに人が仲よくなるためには大きな作用なのかもしれない…
…
continue reading
LAMY サファリのピンクと、ジャポニカ学習帳 漢字練習91字(十字補助線入り)の組み合わせでやってます。 3年生の息子のノートより文字サイズがでかい! ご意見、ご感想はTwitterのハッシュタグ#ごりゅごcastかお便りフォームにお送りください。
…
continue reading
今回は東畑開人さんの 『ふつうの相談』を紹介しました。倉下の考え方に大きな影響を与えてくれた一冊です。 書誌情報 * 著者 * 東畑開人 * 1983年東京生まれ。専門は、臨床心理学・精神分析・医療人類学 * 博士(教育学)・臨床心理士 * 『心はどこへ消えた』『なんでも見つかる夜に、こころだけが見つからない』『聞く技術 聞いてもらう技術』など著作多数 * 出版社 * 金剛出版 * 出版日 * 2023/8/16 基本的に、ケアの現場で働く人向けの内容であり、それも少し硬めの構成になっています。著者の一般向けの著作(『心はどこへ消えた』や『なんでも見つかる夜に、こころだけが見つからない』)に比べると、少しだけ対象読者は絞られています。それでも、難解な理論展開などはなく、理路も明晰なので、じっ…
…
continue reading
面白かった本について語るPoadcast、ブックカタリスト。今回は『会話の科学』について語ります。 今回は、なんだか久しぶりにごりゅごが普通に本を紹介する回だった印象です。(自分の本の紹介とか、ゲスト回などが多かった) 最近は、ブックカタリストで紹介する本がどんどん「今でも印象に残っている本」という方向に変化してきています。 読み終えた直後におお!すごい!と感じた本ではなく、読み終えて数ヶ月経って、この本は面白かったなあ、と思えるような本を紹介しているようなイメージです。 あくまでも自己評価なんですが、そういう本を紹介する方が自分の頭がきちんと整理されて、結果いい感じに紹介が出来るようになってきたような感じがします。 さらに言うと、そういう本は「普通にちゃんと読書メモを残す」ことさえしていれ…
…
continue reading
今回は、オリバー・バークマンの『HELP! 「人生をなんとかしたい」あなたのための現実的な提案』を取り上げました。 バークマンの本は、『限りある時間の使い方』に続いて二回目です。長く続けていると徐々にこういうかぶりも出てきますね。それもまたよしです。 書誌情報 * 著:オリバー・バークマン * 1975年リヴァプール出身 * 『限りある時間の使い方』かんき出版 (2022/6/22) * 『ネガティブ思考こそ最高のスキル』河出書房新社 (2023/3/25) * 原題 * Help !How to become slightly happier and get a bit more done * 翻訳:下隆全 * 出版社:河出書房新社 * 出版日:2023/4/26 * 2014年8月東邦出…
…
continue reading
面白かった本について語るPoadcast、ブックカタリスト。今回は『アトミック・リーディング』について語ります。 『アトミック・リーディング』(内容紹介) 今回紹介する本は、去年ごりゅごが書いた本『アトミック・シンキング』の続編的な内容のものです。 (去年書いた本の紹介はこちら→BC044 『アトミック・シンキング: 書いて考える、ノートと思考の整理術』) 去年書いた本の中で一番反応が多かった「読書と書くこと」についてをより深めた、という感じの内容です。 と同時に、この本を書いた理由と言うのは世の中でよく見かける「速読」「多読」「コスパ」「タイパ」みたいな用語に対するアンチテーゼ的な思いもたくさん込めています。 そして、こうやって自分が思ってたことを本にぶつけると、自分の感情が書くことによっ…
…
continue reading
🐷 ギター(YAMAHA Revstar RSS02T サンセットバースト) qingping 空気品質モニター 車(SUBARU クロストレック) 👠 車の上から視点ガイド Apple Pencilのペン先ペンシルチップ 🖍️🎉 Apple Pencilがソフトタッチな書き心地になる「Pencil Tips」(5/14) ご意見、ご感想はTwitterのハッシュタグ#ごりゅごcastかお便りフォームにお送りください。
…
continue reading
今回のテーマは「忘却と知的生産」。以下の二冊の本を題材に、知的生産において「忘れる」ことがいかに大切なのかを考えてみます。 * 『まちがえる脳 (岩波新書 新赤版 1972)』 * 『忘却の整理学 (ちくま文庫 と-1-10)』 Scrapboxのページは以下。 ◇ブックカタリストBC068用メモ - 倉下忠憲の発想工房 書誌情報 * 『まちがえる脳 (岩波新書 新赤版 1972)』 * 著者 * 櫻井芳雄 * 出版社 * 岩波書店 * 出版日 * 2023/4/24 * 内容紹介 * 人はまちがえる。それは、どんなにがんばっても、脳がまちがいを生み出すような情報処理を行っているから。しかし脳がまちがえるからこそ、わたしたちは新たなアイデアを創造し、高次機能を実現し、損傷から回復する。そのよ…
…
continue reading
以下のお店で委託販売を行いました 楽器の委託販売 – ロッキン 中部地区最大級の楽器専門店 :: 平野楽器 ロッキン ご意見、ご感想はTwitterのハッシュタグ#ごりゅごcastかお便りフォームにお送りください。
…
continue reading
今回はゲスト回です。『逆境に負けない 学校DX物語』の著者である魚住惇さんをお招きして、本に関するお話をお聞きしました。 書誌情報 * 著者 * 魚住 惇(うおずみ・じゅん) * Twitter:@jun3010me * Blog:さおとめらいふ – 魚住惇のブログ * Substack:こだわりらいふ Newsletter * プロフィール: * 1986年愛知県春日井市生まれ。 * 日本福祉大学を卒業後、期限付任用講師、非常勤講師、塾講師を経て2015年より愛知県立高等学校の情報科教諭となる。iPadとHHKBが大好き。iPadはProモデルを毎年買い替える。趣味は珈琲と読書とサーバーいじり。WordPressの勉強として大学時代から書き続けているブログ「さおとめらいふ」は15年目を迎え…
…
continue reading
ひとまずは、Obsidian Publishをそのまま使いつつ、ブログ的な記事を更新していってます。 🏠 - ナレッジスタック - Obsidian Publish ご意見、ご感想はTwitterのハッシュタグ#ごりゅごcastかお便りフォームにお送りください。
…
continue reading
reuseman/flashcards-obsidian: 🎴 An Anki plugin for Obsidian.md ご意見、ご感想はTwitterのハッシュタグ#ごりゅごcastかお便りフォームにお送りください。
…
continue reading
1
BC066 『Remember 記憶の科学:しっかり覚えて上手に忘れるための18章』
1:08:13
1:08:13
「あとで再生する」
「あとで再生する」
リスト
気に入り
気に入った
1:08:13
面白かった本について語るPoadcast、ブックカタリスト。今回は『Remember 記憶の科学:しっかり覚えて上手に忘れるための18章』について語ります。 今回の本は、いわゆる「記憶」系のことを学ぶ一冊目として非常に素晴らしい、と感じた本でした。そして、本編でも語っていることですが、記憶について考えるときに重要なのは「忘れる」ということ。それについてもきちんと忘れずにカバーされている、というのも本書の好印象の理由になっています。 私たちがものごとを「理解」できるのは、見たこと聞いたことすべてを覚えておくことができないから。一部を「忘れる」から、それを自分の中で整理して、自分自身に取り込んでいける。 結局のところ、人類の大半の脳が「忘れる仕様」になっている(本書では「なにもかも覚えている人」…
…
continue reading
Obsidian Publishをブログ的に使い始めました →ポケモン工芸展を見に金沢へ行ってきた - Obsidian Publish ご意見、ご感想はTwitterのハッシュタグ#ごりゅごcastかお便りフォームにお送りください。
…
continue reading
https://twitter.com/haruna1221/status/1663097462796734464?s=20 ご意見、ご感想はTwitterのハッシュタグ#ごりゅごcastかお便りフォームにお送りください。
…
continue reading
今回は好例の三冊セットでお送りします。 * 『英語は10000時間でモノになる ~ハードワークで挫折しない「日本語断ち」の実践法~』 * 『こころを旅する数学: 直観と好奇心がひらく秘密の世界』 * 『プログラマー脳 ~優れたプログラマーになるための認知科学に基づくアプローチ』 書誌情報などは、以下のページ(のリンク)からどうぞ。 ブックカタリストBC065用メモ - 倉下忠憲の発想工房 『英語は10000時間でモノになる』 ポイントは、知識英語ではなく感覚英語を身につけよう、という姿勢です。言い換えれば「英語を使おう」ということ。英語を「学んで」使えるようになるのではなく、使おうとすることを通して使えるようになる、という道筋はしごくまっとうなものと言えます。 で、その「使おう」という姿勢を…
…
continue reading
はるなさんのiPad セミナーを、はじめてリアルタイムで聞きました。 描画モードを使ったかんたん写真合成 - by はるな👠iPad Worker 内容的な興味深さ、それを踏まえて「聞く」ことから得られるものの幅広さ、またセミナーを聞く側としてどういう感覚になるのか。いろいろ得られることが多い体験でした。 iPadだけでプレゼン資料作成が爆速になってきた ご意見、ご感想はTwitterのハッシュタグ#ごりゅごcastかお便りフォームにお送りください。
…
continue reading
面白かった本について語るPoadcast、ブックカタリスト。今回は『体はゆく できるを科学する〈テクノロジー×身体〉』について語ります。 前回の「運動することと食べること、痩せること」シリーズに続く「テクノロジー×身体」がテーマになった本です。 今回の本は(今のところ)今年読み終えた中で一番面白かった本でした。 内容は決して難しいというわけでなく、でも同時に読みながら関連した様々な考えを引き出させる。 あらためて自分が好きな本のジャンルは「テクノロジー」を応用してなにか世の中をよくする話なんだな、ということがわかりました。 そして最後の結論。これもまたごりゅごの好みというか、自分が伊藤亜紗さんを好きだなーと思うところは、この結論の落とし込み方。みんなについて優しく、もっとよい世の中になること…
…
continue reading
Obsidianを複数保管庫で運用する - by goryugo - ナレッジスタック 今後、週に1回を目標に記事を更新していく予定です! ご意見、ご感想はTwitterのハッシュタグ#ごりゅごcastかお便りフォームにお送りください。
…
continue reading
今回は、永田希さんの『再読こそが創造的な読書術である』を取り上げます。 書誌情報 * 著者 * 永田希ながた・のぞみ * 著述家、書評家。1979年、アメリカ合衆国コネチカット州生まれ。書評サイト「Book News」主宰。著書に『積読こそが完全な読書術である』(イースト・プレス)、『書物と貨幣の五千年史』(集英社新書)。 * 出版社 * 筑摩書房 * 出版日 * 2023/3/20 * 目次 * 第一章 再読で「自分の時間」を生きる * 第二章 本を読むことは困難である * 第三章 ネットワークとテラフォーミング * 第四章 再読だけが創造的な読書術である * 第五章 創造的になることは孤独になることである 倉下のScrapboxメモ ネットワークとテラフォーミング 本書で語られる内容をご…
…
continue reading
LISTEN ご意見、ご感想はTwitterのハッシュタグ#ごりゅごcastかお便りフォームにお送りください。
…
continue reading
今回は『習慣と脳の科学――どうしても変えられないのはどうしてか』を取り上げました。 本書は二人とも読んでいた本だったので、いつもとは違ったスタイルになっております。 書誌情報 * 著者 * ラッセル・A・ポルドラック * スタンフォード大学心理学部教授。イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校にてPh.D.を取得。2014年より現職。人間の脳が、意思決定や実行機能調節、学習や記憶をどのように行っているのかを理解することを目標としている。計算神経科学に基づいたツールの開発や、よりよいデータの解釈に寄与するリソースの提供を通して、研究実践の改革に取り組んでいる。著書にThe New Mind Readers What Neuroimaging Can and Cannot Reveal about …
…
continue reading
Hexo ご意見、ご感想はTwitterのハッシュタグ#ごりゅごcastかお便りフォームにお送りください。
…
continue reading
Notes | Substack ご意見、ご感想はTwitterのハッシュタグ#ごりゅごcastかお便りフォームにお送りください。
…
continue reading
今回は、五藤晴菜さんをゲストにお迎えして5月30日発売予定の『+iPad ちょっとした場面で使えるかんたん活用アイデアノート』をご紹介頂きました。 ◇+iPad ちょっとした場面で使えるかんたん活用アイデアノート | SBクリエイティブ 書誌情報 * 著者 * 五藤晴菜 * 出版社 * SBクリエイティブ * 発売日 * 2023年5月30日(火) * ISBN * 978-4-8156-1793-6 * サイズ * A5判 * ページ数 * 192 * 目次 * Chapter0 iPadの魅力を最大限に生かすためには * Chapter1 使いこなすために必ず覚えておきたい基本操作と設定 * Chapter2 メモならiPadにお任せ!誰もが使えるiPadのメモ術 * Chapter3 …
…
continue reading
面白かった本について語るPoadcast、ブックカタリスト。今回は『運動しても痩せないのはなぜか: 代謝の最新科学が示す「それでも運動すべき理由」』と、『科学者たちが語る食欲』の2冊を語ります。 2023年が始まってからごりゅごがずっと続けてきた「運動することと食べること、痩せること」シリーズの最後の回です。 今回はちょうどごりゅごが花粉症の症状が最悪レベルのときと重なって、自分で聞いててかわいそうな声になっておりました。 このシリーズの目論見というか、これらの本を読みながら考えていたことの一つとして、運動すれば無駄な炎症反応が減るので、花粉症の症状も出にくくなすはず、という考えなんかもあったりします。 今年は、Podcast収録ちょっと前まで花粉症の症状はほとんど現れず、去年に比べて運動し…
…
continue reading
ナレッジスタック | goryugo | Substackにて後日詳細をお知らせします。 ご意見、ご感想はTwitterのハッシュタグ#ごりゅごcastかお便りフォームにお送りください。
…
continue reading