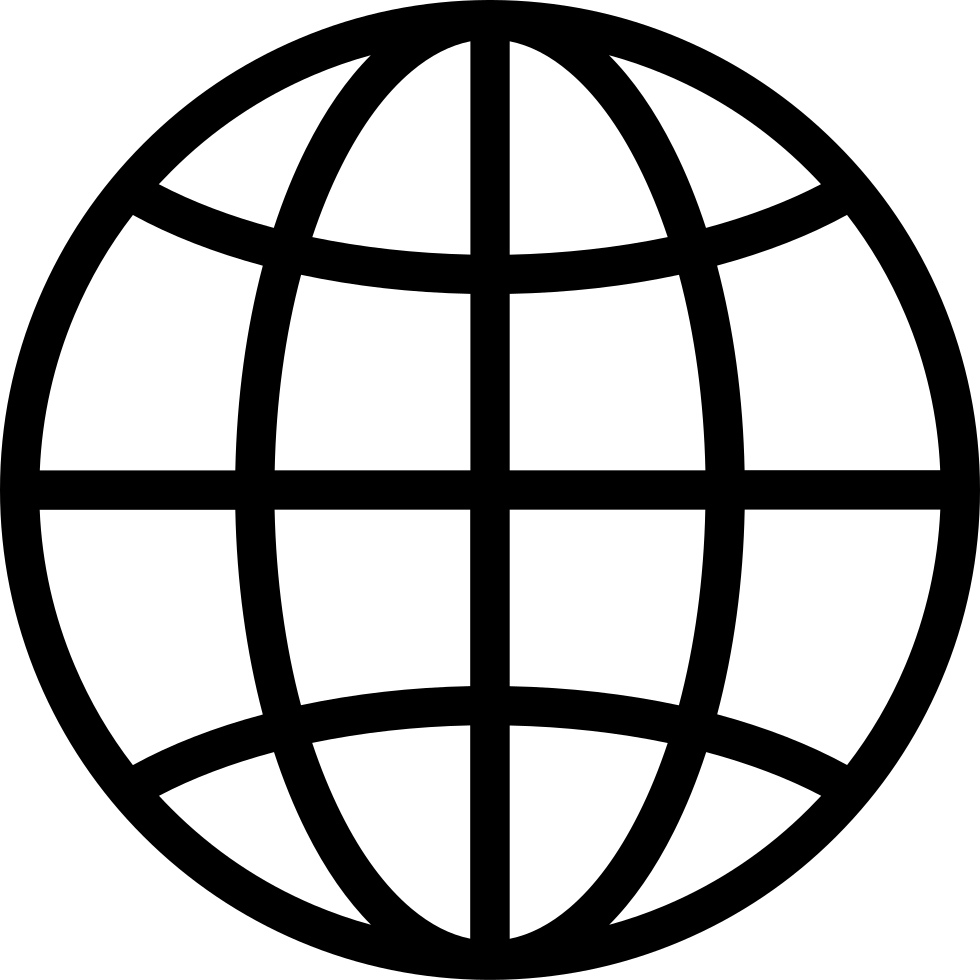【海軍省 練習兵用 歴史教科書】14. 鎌倉幕府の成立
アーカイブされたシリーズ ("無効なフィード" status)
When?
This feed was archived on April 13, 2023 17:21 (
Why? 無効なフィード status. サーバーは持続期間に有効なポッドキャストのフィードを取得することができませんでした。
What now? You might be able to find a more up-to-date version using the search function. This series will no longer be checked for updates. If you believe this to be in error, please check if the publisher's feed link below is valid and contact support to request the feed be restored or if you have any other concerns about this.
Manage episode 277554161 series 2823345
(2)武士の勃興
国民皆兵の制度
我が国は肇国以来、天皇御親率(ごしんそつ)の下に、国民皆兵を建軍の本義とする。
古く氏族制度時代には 大伴・物部の二氏が 同族及び部民を率いて 世々郡司を司どり、ことある毎に 天皇は御親ら軍を率いて出陣し給ひ、各氏族は その部民を率いて軍務に服し、忠誠を盡(つ)くし奉った。
即ち 神武天皇の御東征以来、神武を発揮して皇威を輝かし給うた御歴代の御聖業には、国民こぞって身命を捧げ、これを翼賛(よくさん)し奉ったのである。
兵制の推移
後、大寶令によって徴兵制度が施行され、国民皆兵の制度はますますその實が挙げられることとなったが、やがて平安初期になり 国内統一の御事業が概ね完成せられてからは、専ら東国の武技に秀でたものだけが健皃兵(こんでんへい)・随身兵(ずいじんへい)として宮門を護衛することとなり、ここにはじめて武事を専らとするものの発生を見た。
地方武士の発生
その後、藤原氏擅権(せんけん)の時代を通じて 律令制度が次第に弛(ゆる)み、権門勢家(けんもんせいか)が 荘園として多くの土地を私有するに及び、藤原氏一門の栄華文弱(えいがぶんじゃく)がこれに伴って社会の秩序は次第に乱れ、特に地方は騒然(そうぜん)たる状態となった。
ここに於て地方の豪族は自衛のため私兵を養い、武技を練って自ら秩序の維持に任じ、やがて次第に勢力を得て 地方に台頭してきた。
これが地方武士の発生である。
源平二氏の興起
かくて平安末期になり、これら武装した豪族のうちから その統領(とうりょう)して大なる力を有するものが次第に現れてきた。
これらは多く臣籍(しんせき)に降下せられた皇族、或いは中央の貴族であって、藤原氏が政治を私して権勢を擅(ほしいまま)にしたため、中央に志を得ないこれらの貴族は 地方に移住し、家名を貴ぶ地方武士に推戴(すいたい)せられて その統領となったものであった。
その中でももっとも著しく現れたものが、桓武天皇(かんむてんのう)の曾孫高望(たかもち)王からでた平氏と、清和天皇の御孫経基(つねもと)王からでた源氏とであった。
二氏の対立と平氏の滅亡
源氏は古くからたびたび東国の鎮定にその武名を轟(とどろ)かせて 勢力を東国に扶植(ふしょく)したのに対し、平氏は瀬戸内海の海賊を討って西国に勢力を擴張(かくちょう)し、やがて二氏は地方の治安の維持に成功して中央に進出し、遂に両者の勢力は対立することとなった。
その後、保元(ほげん)・平治(へいぢ)の両乱によって 平氏はその勢力が極めて盛となり、清盛(きよもり)に至って 平家一門はすべて高位高官に登り、遂に藤原氏に代わって 一時政治の実権を握った。
しかし清盛の横暴が募るに及んで 諸国の源氏は各地に蜂起(ほうき)し、源頼朝(みなものとのよりとも)はこれに応じて鎌倉に兵を挙げ、遂に寿永四年(皇紀1845年)、長門(ながと)の壇浦(だんのうら)に全くこれを滅した。
鎌倉幕府の成立
頼朝は平氏滅亡の後もなほ鎌倉に留まって 士風剛健な東国に勢力を養ひ、建久(けんきゅう)3年(皇紀1852年)、征夷大将軍に任ぜられて 幕府を鎌倉に開いた。
かくて頼朝は武力を以て県内の秩序を恢復(かいふく)し、武士道を奨励してこれに基づく質実剛園(しつじつごうけん)な政治を行ったから、藤原氏の専横(せんおう)以来、悪政と争乱に苦しんだ地方武士はみな幕府の親政に服し、政治の実権は幕府に移り、遂に武家政治の基礎が定められることとなったのである。
109 つのエピソード